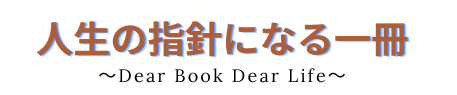「読書を楽しめない大人へ贈る!『仕事と趣味の両立』を叶える方法を考察 - 労働と読書の歴史から見る日本の課題」
- 夢を現実に変える最強のパートナーなぜ働いていると本が読めなくなるのか 心を豊かにする習慣を築くための指南書 ショップ:楽天ブックス
価格:1,100 円
|
目次
「趣味が楽しめない大人たちへの共感と挑戦」
私たちの生活の中で、仕事と趣味の両立が難しいと感じたことはありませんか?それは特に大人になるにつれて顕著になりがちです。
読書や趣味を大事にしたいと思いつつも、仕事のプレッシャーに押しつぶされてしまう…。
このような状況に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
三宅香帆さんの新著作「人類の永遠の悩みに挑む!」は、まさにそのような境遇の中で奮闘している人々の心に響く内容になっています。
この本は、労働と読書の歴史を深掘りし、「仕事と読書」がいかにしてすれ違ってしまったのか、その変遷を辿ります。
著者自身も兼業で執筆活動を続け、多忙な生活を送ってきたからこそ、リアルな視点で「仕事に追われて趣味が楽しめない」という苦悩を追求しています。
彼女の視点を通して、私たちは日本人の「仕事と読書」における根本的な問題点を見つめ直すことができます。
それは単に労働時間の問題ではなく、社会全体に根付いた文化や価値観の問題でもあるのです。
労働と読書は両立しないのか?
序章では、「労働と読書は両立しない?」という一見シンプルな疑問に立ち返ります。
しかし、それは決して単純な話ではありません。
私たちの多くは、仕事と個人的な趣味を両立できずに挫折を感じることが多いです。
特に現代では、仕事に対する求められる基準や成果が高く、自己成長やビジネススキルの向上を常に求められています。
この章では、著者が提示するのは、労働がどのようにして個人の時間を支配するようになったかという歴史的な背景です。
日本の働き方が如何に変化し、労働そのものが人生を左右する大きな要素となったのかを学ぶことで、現代における仕事観の形成過程を理解できます。
とはいえ、ただ愚直に「両立できない」と強調するのではなく、過去の事例や変遷を辿ることで、なぜ今両立が難しいと感じるのか、その本質を探ろうとするのです。
サラリーマンと書物の歴史的な関係
歴史を振り返ると、サラリーマンがどのように書物と関わってきたかは非常に興味深いものがあります。
明治時代以降、労働意識の変化とともに、読書の目的や方法も劇的に変わってきました。
労働を煽る自己啓発書が生まれた背景や、それがどのように影響を及ぼしたかを明治時代から現代に至るまで詳細に追跡しています。
特に大正時代には「教養」が鍵となり、サラリーマン階級と労働者階級の間に明確な線が引かれるようになります。
しかし、サラリーマンと読書の関係は、単なる階級や地位だけでなく、個々の内面的な発展や自己啓発の手段としても重要でした。
それは当時から今に至るまで変わらず、むしろ仕事が忙しくなった現代において、その意義が見直されつつある感があります。
このような歴史的背景を理解することで、現代人が抱える悩みがいかに歴史的な文脈の中で生まれたものか知ることができます。
そして、それを知ることで今抱える問題をどう受け止め、どう改善していくべきかを考える手助けができるのです。
平成以降のビジネスマンのアイデンティティー形成
昭和から平成を経て現代に至る中で、日本社会におけるビジネスマンのアイデンティティは劇的に変化しました。
特に1970年代以降、企業内でのキャリア形成が重視され、「ビジネスマン」というワードに象徴されるような、仕事を自己実現の場とする流れが本格化しました。
しかしこの流れは、仕事と私生活の境界を曖昧にし、趣味や読書に費やす時間が減少する理由にもなります。
それは、生活のメリハリあるいは個人の充実感を損なう結果を生み出し、幸福度の低下につながることもあるのです。
三宅香帆さんは、こうした時代背景を経済的、文化的観点からも捉え、現代の私たちがどのようにこの問題を内面から解決できるのかを模索しています。
そのような中で、読者はどんな視点を持つべきか。
本書は現代の悩みを、その歴史的脈絡の中で理解し直す手助けをしながら、眼の前に立ち塞がる壁を取り除くヒントを与えてくれます。
読書は人生の「ノイズ」なのか?
本書で特に目を引くテーマの一つが、2010年代の章にある「読書は人生のノイズなのか?」という問いかけです。
仕事や生活に追われ、趣味や楽しみに費やせる時間が減りがちな現代では、あたかも時間を浪費するように思われがちな読書。
果たしてそれはノイズなのでしょうか?
この章では、ノイズと思われがちな時間こそが、実は私たちの精神を豊かにし、本来の自分を取り戻す重要な時間であると言います。
これは決して単なる言葉遊びではありません。
現代社会において、どのようにして自分の時間を確保し、充実させるか、その具体的な方法や考え方を示しているのです。
三宅香帆さんの視点は非常に新鮮で、心の奥底にある願望に触れ、「読書を楽しむことこそがノイズではなく、必要な時間だ」と説得力をもって語っています。
この部分を読み進めるうちに、忙しい日常の中でもっと読書を大事にしたい、という気持ちが自然と湧き上がってくるでしょう。
全身全霊をやめるということ
最終章の「全身全霊をやめませんか」は、本書の主題をまとめ上げる重要なパートです。
この章では、読書や趣味に対する偏見を取り除き、自己を知ることの大切さを強調しています。
仕事に全身全霊を注ぎ込むだけでなく、いかにして趣味や読書を通じて自己を認識し、充実した生活を築けるのか。
現代において、大事なのはバランスです。
何事にも全身全霊で取り組むのも素晴らしいことですが、自分にとって何が最も重要なのか、その優先順位を見極めることも重要です。
全身全霊をやめ、その代わりに、自分自身の心の声に耳を傾けてみる。
この指摘は、仕事と趣味を両立させたいと願う多くの人々にとって非常に示唆に富みます。
本書を通じて、仕事と趣味が両立しないという問題を抱える読者も、少しずつ考え方を変え、より充実した生活のための第一歩を踏み出す勇気をもらえるのではないでしょうか。
まとめと読書の楽しみ方
「人類の永遠の悩みに挑む!」は、我々の内面を豊かにし、また社会的な背景を考える上で非常に貴重な一冊です。
その内容は単なる歴史分析にとどまらず、読者が直面する問題を多角的に捉え、具体的な解決策や新たな視点を提案する力作です。
著者の三宅香帆さんは、歴史や文化の変遷を丁寧に紐解きながら、現代の悩みをどう乗り越えられるかを親身に考えてくれます。
特に、働きながら読書を大切にするコツを伝授してくれるなど、読者にとって一つのヒントとなっています。
このレビューを読むことで、本書に興味を持った方、そして労働と趣味の両立に関心がある方は、ぜひ手に取って感じてみてください。
その中で、きっと新たな発見や気づきが見つかることでしょう。
ショップ:楽天ブックス
価格:1,100 円
|
2025年6月15日
関連記事
著者名: 人事行政研究所出版社名: 人事行政研究所ISBNコード: 9784908252471発売日: 2025年08月 (件) 2026年1月15日 自己啓発 |
「あなたはマザコンよ、正真正銘の」妻に言われ、腹立ちまぎれに会社の女の子と寝てしまったぼく。夫より母親を優先する妻のほうこそ、マザコンではないのか。苛立つぼくの脳裏に、死の床か... 2026年1月10日 自己啓発 |
100年以上読み継がれる「人生論」の源流を大公開。現代の自己啓発はすべてオリソン・マーデンから始まった!19世紀アメリカの自己啓発家が現代に遺した、誰もがあてはまり、誰もが共感できる... 2026年1月5日 自己啓発 |
4つの図で、思考はたちまち前進する!・視野を広げ、目標達成をするーーおでん図・現状を理解し、課題を整理するーー田の字・本質を理解し、打ち手を考えるーーループ図・継続的に、打ち手を... 2025年12月25日 自己啓発 |
この法則に従うとあなたの夢はかなう。なぜ嫌なことばかり起こるのか?夢を実現させるためのパワフルな法則とは?本当にやりたいことを見つける方法とは?全世界数百万人の人生を変えたディ... 2025年12月22日 自己啓発 |